どうやったらなれるの? 管楽器リペアマンになるまでの道のり管楽器リペアマンというお仕事 #4

「楽器修理の仕事ってかっこいい!」「自分の手で楽器を直してみたい!」
そんな風に思ったことはありませんか?
これまでの連載では、実際の修理現場やリペアマンの愛用道具を紹介してきました。今回は、いよいよ本題。「管楽器リペアマンになるには、どうすればいいの?」という疑問にお答えします。
1. そもそもリペアマンってどんな仕事?
管楽器リペアマンは、壊れた楽器を直すだけでなく、演奏者の「こう吹きたい」「こう響かせたい」という思いを形にするサポーターです。
リペアの対象は、ピストンやキー、抜差管、タンポ、バネなど多岐にわたり、繊細な作業と高い精度が求められます。
作業はただの技術だけでは成り立たず、音楽への理解と、奏者とのコミュニケーション力も必要です。

2. リペアマンになる方法は主に3つ!
① 専門学校に通う(おすすめ)
もっともポピュラーな方法が、楽器修理の専門学校に進学することです。
学校では、楽器の構造から工具の扱い方、基本的な修理方法まで体系的に学ぶことができます。
2年間から3年間の勉強の後、卒業後は、楽器店のリペア部門や、修理工房、メーカー系のリペア職などに就職する人が多いです。
ちなみに僕は名古屋にある中部楽器技術専門学校を卒業しています。
② 工房に弟子入りする(レアケース)
昔ながらの方法で、職人の元に直接入り、仕事を覚えていくパターンです。
未経験から始めることもありますが、近年は受け入れが減ってきています。
弟子入りは狭き門ではありますが、現場で学べること、ベテラン職人の技術を肌で感じられる点は魅力です。
③ 楽器店・メーカーで働きながら学ぶ
店舗やメーカーに就職し、社内研修やOJTで技術を習得していく方法です。
入社当初は販売や接客をしながら、徐々に修理の道に進むスタイルです。
ある程度の音楽経験や楽器知識があると有利になります。
3. どんな人が向いている?
リペアマンには、次のような資質が求められます。
- 手先が器用で、細かい作業が好きな人
- 地道な作業にも集中して取り組める人
- 楽器や音楽が好きで、奏者の気持ちを想像できる人
- 聞き上手で、コミュニケーションを大切にできる人
また、修理は「失敗が許されない現場」。一つのミスが音に直結するため、常に冷静な判断と丁寧な作業が必要です。
技術にばっかり目が向いてしまうんですけど、コミニケーションが取れる人が向いていると思います。

4. 資格は必要? 専門知識は?
国家資格などはありませんが、信頼と実力がものを言う世界です。最初はコルク交換や抜差管調整といった基本作業から始め、徐々に複雑な修理へとステップアップしていきます。
音大を卒業している必要はありませんが、楽器の演奏経験があると、奏者の立場に立った調整ができるようになります。
5. 現場のリアル:就職・収入・キャリアパス
最初のうちは修理補助やメンテナンス業務からスタートすることが多く、技術が認められると担当業務が広がっていきます。収入は決して高くはありませんが、経験を積み、技術力を高めることで、独立や工房開設といった道も開けます。
「音で感動を生む仕事」として、長く続ける人も多い職種です。
今、ぼくは管楽器修理士の待遇をよくすることに励んでいます。
給料は今後良くなっていくかもしれませんね。

6. 修理道具に興味がある方はこちらも!
前回の記事では、実際のリペアマンが愛用している道具を詳しく紹介しています。こちらもぜひご覧ください。
🔗 管楽器リペアマンというお仕事#3 楽器修理のプロが愛用!現場で欠かせないリペア道具TOP3とは?
最後に
「楽器を直す」ことは、単に壊れたものを元に戻すだけでなく、奏者の思いを音にのせて届けるための、大切な橋渡しです。
少しでも「リペアマンになりたい」と思ったあなた。まずは学校の見学や、近くのリペア工房を訪ねてみるのも良いかもしれません。
あなたの手で、次の“音”を生み出してみませんか?

この記事の著者
管楽器リペアマン
服部 悟
服部 悟
岡山県出身。10代の頃より吹奏楽に親しみ、専門学校卒業後、楽器店勤務を経て独立。
2000年代より本格的に管楽器修理・販売・教育事業に携わり、現在は「株式会社服部管楽器」および関連スクールの代表として、多くの奏者とリペアマンを育成している。
自身の現場経験を活かし、リペア職人の社会的価値向上を目指して活動中。
noteに活動記録あり https://note.com/hattorikangakki
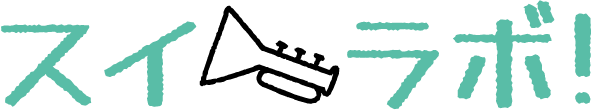
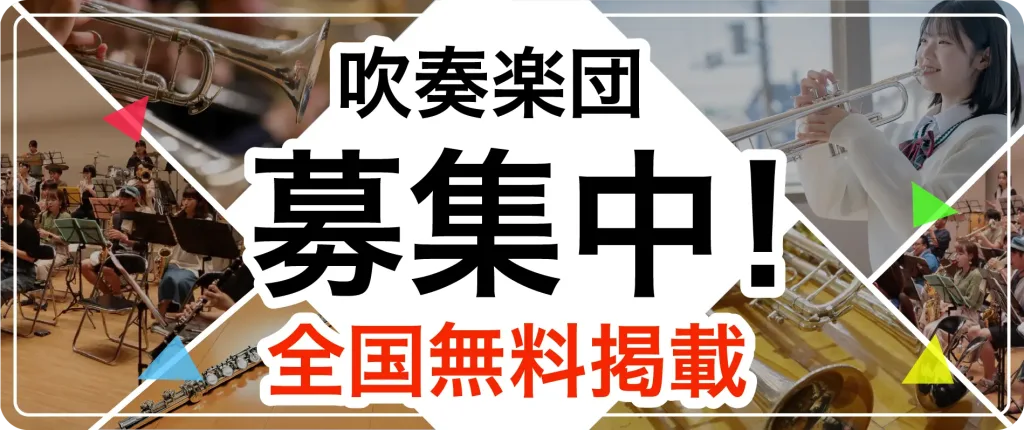

コメント