チューニングはなぜA=442Hz?〜音の基準が違うとどうなるの?吹奏楽の音合わせのヒミツ〜【吹奏楽豆知識】
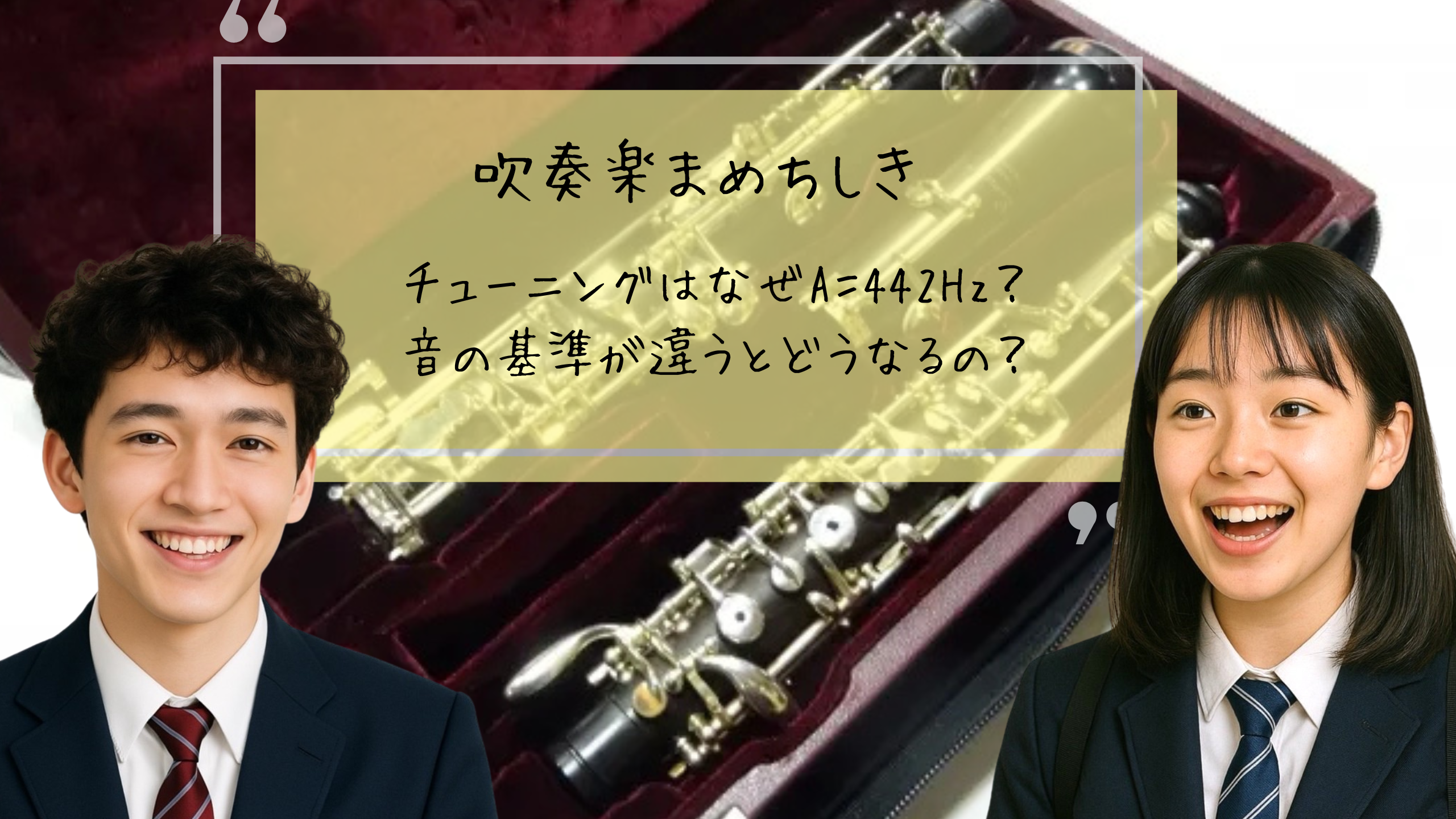
 智頭先輩
智頭先輩ねぇ琴葉、今日の合奏、なんか音が“モヤッ”としてなかった?



うーん……たしかにハーモニーが濁ってたっていうか。
私の音がズレてたんですかね?(じと目)



いやいや、誰のせいとかじゃなくて!
それ、ピッチ(Hz)の問題かもよ。



ピッチ?あーまた出た、“先輩用語”。
っていうか……442Hzって何?おいしいの?
■「A=442Hz」ってどういう意味?
吹奏楽部でのチューニング中は多くのバンドでB♭で行いますね
ただ、その時に「442でチューニングしてね!」という場面、ありますよね。
このときの「442」というのは「A=442Hz」のこと。
“ラ”の音を1秒間に442回振動する音”として合わせましょう”という意味です。
この数字は、音の“高さ”の基準。基準がズレると音程のバランスも変わってしまうため、みんなで音を合わせるにはとても大切なんです。
吹奏楽はAの音を基準にして、B♭でチューニングしているということですね。


ちなみにA=442Hz のとき、B♭(シ♭)の周波数は約468.28Hzだそうです。
覚えなくてOKです。
■そもそもなんで「442Hz」なの?どうやって決まったの?
実は、「A=442Hz」は世界共通のルールではありません。
時代や場所、ジャンルによって、基準となる「Aの音」は少しずつ変わってきました。
🎼 歴史をさかのぼると…
| 時代/場所 | 基準ピッチ(A) |
|---|---|
| バロック時代(1700年頃) | 約415Hz〜430Hz |
| モーツァルト時代(18世紀末) | 約430Hz前後 |
| 19世紀(フランス) | 435Hz ※ディアパゾン・ノルマル |
| 1939年(国際標準) | 440Hz |
| 現代の吹奏楽/オケ | 442Hz〜445Hz(団体により異なる) |
昔は場所や楽団によってバラバラでしたが、1939年に国際会議で「A=440Hz」が世界標準として決まりました。ただ、日本の吹奏楽では、より明るく、響きがよいことから「A=442Hz」が主流になってきたのです。
※「ディアパゾン・ノルマル(Diapason Normal)」は、19世紀にフランスで決められた音の高さ(基準ピッチ)の国際標準のことです。


・その音を再現して測定したところ――🔔 A=422.6Hz(±0.5Hz)
→ 現在より20Hzほど低いピッチだったことが分かっています。
■A=442Hzが好まれる理由
◎1. 明るくてハリのある音に聞こえる
高めのピッチは、音が前に出て、ホールや屋外でもよく響きます。
◎2. 木管楽器と相性がいい
フルートやクラリネットなどの木管楽器は、少し高めの音の方が吹きやすく、音もまとまりやすい傾向があります。
■ピアノと合わせるときはどうするの?
ピアノはA=440Hzが基本。
そのため、吹奏楽(A=442Hz)と合わせるとほんの少し音がズレる可能性があります。
🎹 解決策は?
- 吹奏楽側がA=440Hzに下げて合わせるのが基本。
- ピアノは簡単に調律を変えられないため、可変な側が合わせるという考え方です。
■ではグロッケンやシロフォンはどうするの?
🔔 グロッケン(グロッケンシュピール)
- 最近のモデルはA=442Hzで調律されており、吹奏楽との合奏ではそのままで問題なし。
- ピアノとの共演時にピッチ差があっても、音の持続が短いためあまり気になりません。


🥁 シロフォン(木琴)
- 同じくピッチ変更はできませんが、グロッケンより音がはっきり立つ分、ズレが少し目立ちやすい楽器です。
✅ 実践でできる工夫:
- 打つ強さを調整して目立ちすぎないようにする
- ピアノと完全ユニゾンで演奏する場面は控えめに
- ステージ上で少し距離を取って配置するなど、アンサンブル全体で工夫する
■プロのオーケストラでもピッチはバラバラ?
| 楽団名 | 基準ピッチ |
|---|---|
| NHK交響楽団 | A=442Hz |
| ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 | A=443〜445Hz |
| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 | A=443Hz前後 |
| ボストン交響楽団 | A=444Hz |
| シカゴ交響楽団 | A=442Hz |
それぞれの楽団が、自分たちの響きに合わせた基準を採用しており、「高め」が主流にはなっています。
■このままどんどん上がっていくの?
いいえ、もう大きくは上がらないだろうという見方が一般的です。
✍️ 理由①:演奏者の負担が増える
金管楽器などではピッチが高いと疲れやすく、演奏の難易度が上がります。
✍️ 理由②:ジャンルによっては低いピッチも使う
古楽(バロックなど)では、A=415Hzなど低いピッチも使用され、多様なピッチの“使い分け”が重視されている時代です。
✍️ 理由③:他ジャンルとの共演がしづらくなる
吹奏楽・合唱・ピアノ・録音制作など、周囲と合わせづらくなるのは大きなデメリット。そのため、A=442〜443Hz付近で安定しつつあります。
■初心者のためのチューニングのコツ
- チューナーのHz設定を確認(440Hz? 442Hz?)
- 木管はウォーミングアップ後に再確認(温まると音程が上がる)
- 金管は疲れると下がるので、支えを意識!
- 周りの音を聴きながら耳で合わせる力を育てよう
■まとめ:ピッチを知れば、もっと音楽が楽しくなる
A=442Hzは、ただの数字じゃありません。
それは、「みんなで同じ方向を向いて、音楽をひとつにするための約束」です。
ピアノやグロッケン、シロフォンのようにピッチを変えられない楽器と一緒に演奏する時は、「どちらが合わせるべきか?」「どう工夫するか?」を考えることがアンサンブルの力になります。
時代によって変化してきた音の基準を学ぶことで、音楽の奥深さが見えてくるかもしれません。
さあ、次の合奏ではチューニングの意味をちょっとだけ思い出してみてくださいね!



結局、たかが2Hz、されど2Hzなんですね。
この世界、意外とシビアだなぁ。



そうそう。耳で聴いて合わせる力こそ、吹奏楽の真骨頂だよ。
Hzの意味が分かれば、チューニングがちょっと面白くなるでしょ?



うん……てことで、次の合奏は“ちゃんと”チューナー見ます。
(※できれば目と耳両方で。)



さすが、後輩の成長がまぶしいぜっ!(どや顔)
じゃ、次は「吹奏楽の中でクラリネットが多すぎる理由」でも語ろっか♪



その話、長くなる予感しかしないんですけど……
\吹奏楽のこと、ぜんぶここに /
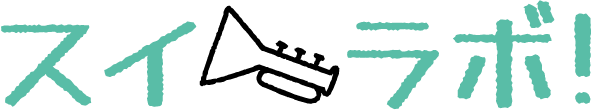
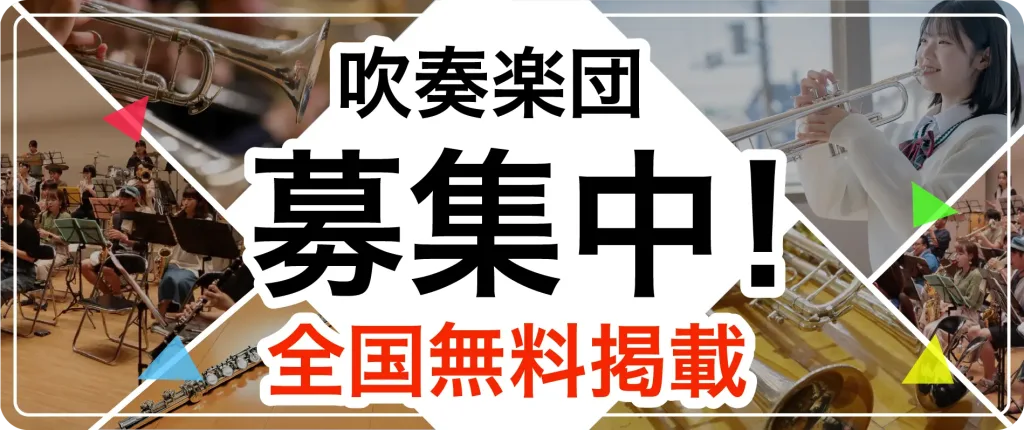

コメント